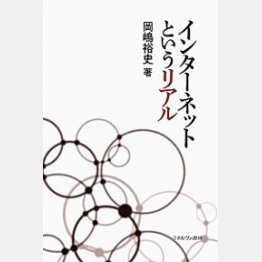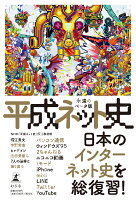長くて短いネットの長い歴史
「インターネットというリアル」岡嶋裕史著
トランプ前大統領のSNSアカウント停止問題などで改めてネットの功罪と歴史が見直されている。
◇
著者は中央大の国際情報学部で教壇に立つ団塊ジュニア世代。自分と同世代か下を「多様な価値観を持つことをよしとする教育を受けた」点が親世代と違うという。だから束縛はイヤ、ムラ社会にも違和感しかない。
ところが個人主義と多様性が「隅々にまで浸透」した現代では自由なのがかえって不自由というパラドックスが生じている。ちょうど自由につながるのが夢だったはずのネット空間が、分断といがみあいの場になってしまったように。
著者は「SNSはインターネットを分断した」という。しかしネットが社会を変えたというより、ネットは「社会の増幅器にすぎない」と指摘する。だが、現代のような「ポストモダン的な社会が現実のものとなったのは、インターネットの登場が契機になっている」とも付け加える。
もとは教科書として書かれた本のようだが、著者はアニメの「新世紀エヴァンゲリオン」などの例を引きながら、新書調の気軽な文体で話をすすめる。SNSで似たような人間とだけ交流すると摩擦のリスクが少ないが、多様性はなくなり外の世界とのトラブルで「炎上」が起こりやすくなる。矛盾にみちたネット社会の「リアル」を説く。
(ミネルヴァ書房 2750円)
「デジタルで変わる子どもたち」バトラー後藤裕子著
生まれたときにはもうスマホがあった世代がいまや中学生。ひところは「デジタルネーティブ」などと持ち上げる安易な風潮があったが、米ペンシルベニア大で英語教育にたずさわる著者はネットも語学も「ネーティブ」が上ということはないという。2歳児に動画を見せて注視の度合いを調べた実験や、紙の絵本とデジタル絵本で理解力にどのぐらいの差があるかの実験など、さまざまな角度から「デジタル世代」の実像に迫る。抽象論に終始せず、スマホの使用と教科書などを読んで理解する「リーディングスキル」の関係などにも広く目を配る。
著者は本書をあくまで入門と問題提起にあるとし、より詳細な実証研究が必要だと説く。大学レベルになるとSNSを使った討論などではふだん発言しないシャイな学生が積極的になるとの結果もあるという。
(筑摩書房 1034円)
「平成ネット史」NHK「平成ネット史(仮)」取材班著
1989年に始まった平成の30年間はインターネット普及の時代とぴったり重なる。そこから発想されたNHKの番組を書籍化したのが本書だ。そこで番組に登場した有名人たちのコメントも随所に出てくる。ホリエモンこと堀江貴文、落合陽一、ヒャダイン、「ブログの女王」と呼ばれたタレントの真鍋かをりまで。最初の飛躍は「ウィンドウズ95」の発売。深夜に長蛇の列ができた光景を覚えている人も多いだろう。あれが「歴史の転換点」だったと本書はいう。
それまでは「とんねるず」の石橋的なノリで場を仕切るヤツが世界の中心にいたのが「陰キャラやオタク」が「夜に出られるようになった」というコメントが笑える。
(幻冬舎 1870円)