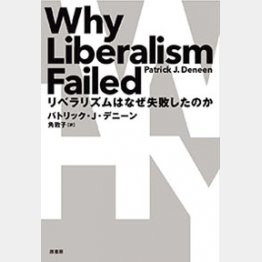同じ高級アパートに住む3家族の扉の向こう
「3つの鍵」
いまどきの映画監督には珍しく、イタリアのナンニ・モレッティは堅物である。コメディーの「ローマ法王の休日」でさえ、生真面目でリベラルで、そのぶん悩みも深い。
本人も自覚的で、自作にもしばしば悩める左派の映画監督を登場させる自己戯画ぶりだ。近年は戯画ですまなくなり、前作の「母よ、」では主人公を女性監督に設定。私生活と仕事の双方でしこたま悩みを抱えるさまに迫っていた。
若いころはゆったりとユーモアある逸材だったのにと思う半面、いまの時代、笑ってすませられるほど能天気になどなれんよねえ、と共感したくもなるのである。
そんなカタブツの新作が9月半ば封切りの「3つの鍵」。ローマの高級アパートに住む3家族。典型的な「中の上」同士のご近所関係が、ある事件で崩れてゆく。エリート裁判官の息子は落ちこぼれで、老夫妻の夫は認知症の兆候。出産間近の妻は夫が出張で不在がちで鬱の気配がにじむ。
裁判官の夫役は俳優でもあるモレッティ自身。左派エリートにありがちな、よかれと思って息子をつぶす高圧的な父を演じている。要は時代の激変と矛盾あふれる世の中をキレイゴトの理想論でやり過ごしてきたリベラルの、つきつめた自己批判なのだ。
実際、冷戦後の30年は新「自由」主義の名で大衆を食い物にするエリートきどりの尻馬にリベラルが乗った、偽善と堕落の時代だった。それは果たしてどこへ行くのか。
パトリック・J・デニーン著「リベラリズムはなぜ失敗したのか」(角敦子訳 原書房 2640円)は、個人主義のきわまった社会は民主主義(リベラル・デモクラシー)を突き抜けて自由専制主義(リベラル・オートクラシー)にたどりつくと警告した米ノートルダム大政治学者の警世の書。その古典的な姿はオーストリア=ハンガリー帝国。ならば現代の代表は中国だろうか。 <生井英考>