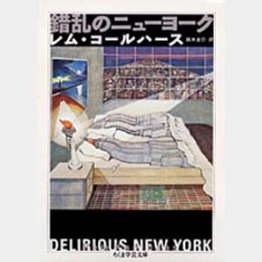ヒップホップが人種を超え化学反応し若者文化に
「All the Streets Are Silent:ニューヨーク(1987-1997)ヒップホップとスケートボードの融合」
90年代半ばのニューヨークでは、かつて場末の肉市場だった地区が最先端のクラブの点在する流行の一帯になっていた。いまは「ミートパッキング」地区として観光地化しているが、当時は人けのない危険な場所にあったのが「クラブ・マーズ」。
ここを拠点にヒップホップが人種を超えた若者文化として急拡大していった過程をふりかえるのが先週末封切りのドキュメンタリー映画「All the Streets Are Silent:ニューヨーク(1987-1997)ヒップホップとスケートボードの融合」だ。
この種の作品はえてして独り善がりのものも少なくないが、本作は平明に、郊外の白人少年の趣味というイメージの強かったスケボーと大都会のスラムの産物とみられたヒップホップが互いに影響し、化学反応を生み出してゆくさまを興味深くたどる。
仲間内で撮った実写映像に加えて当時の関係者のインタビューが多数盛り込まれているが、いずれも中年になった顔つきは穏やかで、ヒップホップも「歴史」になったのだなと感慨が湧き起こる。
そういえば同じ90年代にロックミュージックの博物館なんてものが出てきて、「ロックも歴史になった」などという声も聞かれたのである。
とはいえそんなふうに感じるのは、想像と創造、ふたつの力が枯渇している証しかもしれない。時代が、社会が、そしてニューヨークという街までもが……?
レム・コールハース著「錯乱のニューヨーク」(筑摩書房 1650円)は78年初版の有名な“奇想の建築論”。資本主義の砦たるニューヨークが欲望のままに正統的な近代建築を破砕した歴史をオランダの建築家が皮肉に論じて世界の建築界を扇動した。いまのニューヨークにあのころのような野蛮な活力はあるだろうか。そして21世紀はどこへ向かうだろうか。 <生井英考>