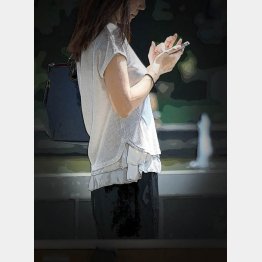<33>早貴被告からの返答「どうして私が別れなければならないんですか」
「何がですか?」
「だからドン・ファンとさ」
声の調子からすると「別れますから」という返事が来ると確信した。ところが、である。
「どうして私が別れなければならないんですか? 私から別れると言ったことはありませんから」
「本当かい? だって電話に出なくなったんだろ?」
「それは忙しかったから出なかっただけです」
「じゃあ、そのようにドン・ファンに伝えていいんだね」
「ええ、それでいいです」
電話を切って、不思議な感覚に包まれていた。
早貴被告は間違いなくドン・ファンのことを避けている。彼からの電話に折り返すことはしないのだから、忙しいのではなくて面倒だったのだろう。声の調子でしか判断できないが、口ぶりも嫌そうだった。それなのに「別れない」という彼女に、何か強い意志を感じた。
今までドン・ファンが付き合ってきた何人かの女性とも、同じように電話で話をした。だが、早貴被告のような反応は初めてのことだ。この女の真意が分からない――足が抜けなくなるようなドロドロの沼に入り込んでいくような感覚になった。
まっ、沼に入るのは私ではなくてドン・ファンなのだから気にしなくてもいいはずだけど、この時の嫌な感覚は今でもしっかりと覚えている。
2月8日の早朝、私は新幹線で大阪に移動し、在来線に乗り換えて八尾の駅前に降り立った。=つづく