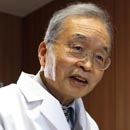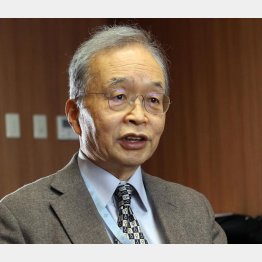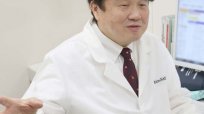93歳のおばあさんが治療した分だけ長く生きた意味
9月に入った頃、おばあさんは急にふらついて歩けなくなり、箸を持つ指の動きもおかしくなりました。病院を受診すると、頭部CT検査で脳にがんの転移が多数見つかり、そのまま入院となりました。担当医からは「何もできないので、このまま様子を見ます」と言われましたが、2日後に「薬は飲めるようですし、もしかして効くかもしれないので1カ月だけでも試してみましょう」と提案がありました。孫娘は同意して、おばあさんは分子標的薬を内服することになったのです。
その薬は担当医も驚くほど効果がありました。起き上がることもできなかったおばあさんがひとりで食事を取れるようになり、トイレにも歩いて行けるようになりました。そして1カ月後には、退院できるくらいまで回復したのです。自宅に帰ったおばあさんは、またいつもの暮らしに戻りました。午後はT君と2人きり、「おーばっぱは引き算ができない」なんて言われながら、同じような日々を過ごしました。
■「あのまま亡くなった方が幸せだった」と言われて…
おばあさんに再び異変が起こったのは、翌年の5月のある夜でした。急に全身の痙攣を起こし、救急車で病院に搬送されました。担当医からは「これまでの内服治療が効かなくなり、脳の転移が増えたために痙攣が起こった」と説明されました。がんの治療は行わず、抗痙攣剤などの点滴や酸素吸入などで様子をみることになったのです。