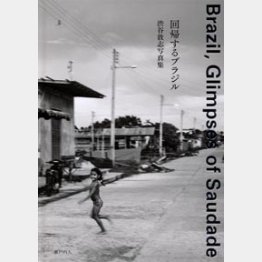「回帰するブラジル 渋谷敦志写真集」渋谷敦志著
若き日に、「世界に触れるような生き方をしたい」という思いを抱いていた著者は、17歳のときにベトナム戦争を記録した一ノ瀬泰造の写真集に出合い、戦場写真家になる決意をする。
しかし、大学1年のときに起きた阪神淡路大震災の被災地に足を運んだ際に、被害の大きさに圧倒され、一枚も写真を撮ることができなかったという。
そんな自分を鍛え直したいと海外留学先に選んだのがブラジルだった。留学は、ブラジル社会の中で働きながら、言葉や文化を体験的に学ぶ研修が主で、1996年春から1年間、サンパウロの法律事務所で働いたという。
以来、ブラジルは氏にとって始まりの場所であり、世界中を旅する日々で人生が思うようにいかないときや、写真を撮ることに思い悩むたびに、回帰する場所となった。
本書は、その1996年から昨年まで、事あるごとに訪ね歩いて撮影してきたブラジル各地の点景を収めた作品集。
勤めていた法律事務所があったサンパウロのセントロ地区のビルの谷間にどこからともなく舞い降りてきたシャボン玉、夜行バスに乗って毎月のように出かけたリオデジャネイロのイパネマの浜辺と双子岩、熱気に満ち音楽が聞こえてきそうなサンバの練習場、夜のとばりがおり昼間の風景とは一転して光が瞬くファベーラ(スラム街)、そして緑の魔境といわれるアマゾンでは、日本からの移民がつくった町トメアスで出会った坂口さんと、アマゾンの内奥へと分け入っていく。
世界を旅しながら、遠くブラジルを思うとき、「サウダージ」という感情に襲われると氏はいう。「過ぎ去った時間への懐かしさ、何かが満たされていない寂寞、心にはあるのに触れることができない哀切」といった思いが凝縮したポルトガル語だ。
サンパウロから600キロ離れたミランドポリス市で28家族の日系・日本人が共同生活しながら営む「弓場農場」や、北東部バイーア州サルバドールのカーニバル、そしてカーニバルを見終えて向かう内陸の荒地セルタンなど、サウダージに導かれるように訪ね、カメラに収めたそのモノクロ作品は、そこに暮らす人々の日常を切り取り、ブラジルという広大な国の素顔に迫る。その一葉一葉の写真が、見る者の心をざわめかせ、その心のうちに今まで感じたことのない「サウダージ」の萌芽を植え付ける。
巻頭と巻末には、ブラジル以外で著者が「サウダージ」を感じた場所として、2000年のアンゴラ、そして2011年の震災直後の福島で撮影された作品が添えられる。
オリンピックで身近になったブラジルを観光気分ではなく、肌感覚で感じられる写真集。(瀬戸内人 3700円+税)