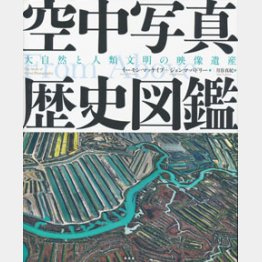「空中写真歴史図鑑」イーモン・マッケイブ、ジェンマ・パドリー著、月谷真紀訳
人類は写真技術を得たことにより、念願だった「神の視点」をついに手にする。
本書は、写真草創期の19世紀中ごろから21世紀の現代まで、その神の視点を手にしたカメラマンが撮影してきた「映像遺産」とも呼ぶべきとっておきの空撮写真を収録した豪華写真集。
ドローンの出現によって、現代では空撮写真のハードルはかなり低くなったが、飛行機が登場する以前の空撮は困難を極めた。
その困難に挑んだのが世界で初めて空から写真を撮影したフランス人のガスパール=フェリックス・トゥールナションなる人物だ。
1858年、同氏が係留した気球に乗って高度520メートルから撮影したパリの凱旋門の写真が残っている。
気球での撮影は安定性に欠け、写真の凱旋門はややぼやけているが、その後に撮影されたベルサイユ宮殿などは被写体の美しさを余すところなく伝える。
同じくフランス人のアルチュール・バテュは、たこに軽量のカメラを取り付け、緩燃導火線でシャッターを作動させる仕組みで撮影した空中写真の刊行物まで出版。
さらに黎明期には、伝書バトを使って医薬品を配送していたドイツの薬剤師が、ハトに装着できるセルフタイマーカメラを開発してフランクフルトとその周辺を撮影している(写真①)。写真は絵ハガキとして販売されたそうだが、技術に目を付けた軍によって空中偵察にも採用されたという。
空中写真の被写体となるのは、街並みだけではない。イギリスの古代遺跡ストーンヘンジ(1906年)や、危険を顧みずスイス・アルプス上空を横断して撮影した写真などもある。この時に撮影された眼下に広がるメール・ド・グラース氷河の絶景(写真②)は、現在も気候変動の影響を特定するために環境問題の専門家らに使用されているそうだ。
また中には3000人もの犠牲者を出した1906年アメリカのカリフォルニア大地震直後のサンフランシスコの惨状をとらえた写真もある。
第1次世界大戦時には空中偵察は敵の動きを察知したり、被害規模を記録するなど現代戦争の一部となっていた。爆撃によって廃虚と化した激戦地ベルギー・イーペルなどの写真が残る。
また原爆投下直後の広島など、第2次世界大戦までは戦争の世紀を象徴するような空中写真が並ぶ。
やがて時代が進むと、空中写真もただ記録することから、表現の一手段としての作品も現れ始める。ウィリアム・A・ガーネットは空中写真を芸術の域にまで高めたパイオニアだ。氏が1953年にモノクロで撮影したクルミ林や、マーガレット・バーク=ホワイトが撮影したトラクターによって耕作された畑などの写真は一幅の絵画のようだ(写真③)。
他にも、資源採掘によって鉱石が流出(2014年)して地球が汚染される様子や、インド・ムンバイの高層ビル群と隣り合わせるスラム街(2016年)などの世界の現実を表すものまで200点を収録。
最後の一枚は、ガスパールから160年後の2018年に撮影されたパリの凱旋門だ。
(原書房 5800円+税)