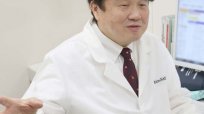(20)そろそろ自分たちで…頼みの叔母から切り出された
私は電話で叔母たちに、見えないけれど深く頭を下げ、母の通院の付き添いをお願いした。しかし、回数を重ねるにつれ、ひとりの叔母がため息をついた。「そろそろ自分たちでなんとかしてくれないか」。そう言われるのは当たり前だ。
私は母がいつまで認知症専門医院に入院していなければならないのかが気になり始めた。数カ月前までは関心を抱いたことすらなかった介護保険についても、すでに調べ尽くしていた。母の今後を決めるためにも、叔母たちに迷惑をかけず我々家族が生活していくためにも、まずは母の介護認定を受けなければならない。もう公的支援に頼るべき時期だと考えた。
後日、実家で見たカレンダーに父は「1」「2」……と数字を書き込んでいた。まるで、母が戻ってくる日を指折り数えるかのように。父は、母が元気になって家に帰ってくるものと強く信じていたのだ。
しかし、母が元通りに実家で生活できることはもはやないだろう。私にはこの頃から、静かな諦めが育っていった。 (つづく)
▽如月サラ エッセイスト。東京で猫5匹と暮らす。認知症の熊本の母親を遠距離介護中。著書に父親の孤独死の顛末をつづった「父がひとりで死んでいた」。