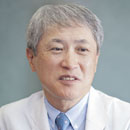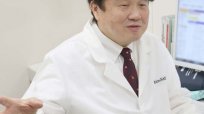iPS細胞で心臓そのものをつくり出すのは極めてハードルが高い
また、以前に取り上げた自己組織を使う心血管修復パッチも同様に、正常に機能しない、またはしなくなってしまったパーツを取り換えて、より長く安全に使い続けるという方向で開発が進んだものといえます。
ここからさらに、iPS細胞を使って僧帽弁や大動脈弁をつくり、傷んで機能しなくなった弁と交換する研究開発が期待されます。心臓弁は構造的には薄くてペラペラなのですが、機能としては非常に高度なうえ、何十年も機能を担う耐久性が求められます。そのため、主にカーボン素材でできている機械弁と、ウシやブタの組織を利用した生体弁という2種類の人工弁がいまだに使われています。長らくこれらを超える医療材料ができていないのです。そんな心臓弁をiPS細胞で生み出すことができれば画期的な進歩ですから、大いに期待しています。
心臓が生きていくための機能を保てなくなるケースは、生まれつき先天性の構造異常がある場合と、生活習慣病などによる影響や経年劣化によって、心筋、心臓弁、血管といったパーツがダメになって起こる場合に大別できます。ですから、iPS細胞を使って心臓そのものをつくり出して丸ごと交換するよりも、それぞれのパーツをつくって、機能しなくなったものを交換していくほうが有用といえます。