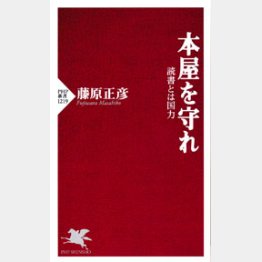「本屋を守れ 読書とは国力」藤原正彦著/PHP新書
数学者で作家の藤原正彦氏によるユニークな教養論だ。藤原氏は、アメリカニズムが日本の教養を破壊したと考える。
<戦後、アメリカ占領軍による言論統制(『閉ざされた言語空間』江藤淳著に詳説)により「戦争は一方的に日本が悪かった」と洗脳されましたが、それがいまだに脈々と生きているのです。エリートだけではなく、日本人一般に至るまで「誇り」を失ってしまいました。そこから「欧米の文化はすべて日本より優れたもの」という恐ろしい錯誤が生まれ、アメリカニズムの浸透すなわち教養の軽視と功利主義の跋扈が始まり、小泉=竹中政権以来の新自由主義、グローバリズムによる構造改革、IT・英語教育礼賛論に至る流れができたのです>
高等教育を受けるとカネになるというような発想自体が教養から懸け離れているのだ。
東西冷戦終結後、アメリカ発の新自由主義が世界を席巻した。影響が日本では「改革ブーム」という形で表れた。
<新自由主義の蔓延に関しては、日本では小泉・竹中構造改革という売国政策の毒がいま、国全体に回っています。小泉政権は郵政民営化で郵貯・簡保を切り分け、アメリカのハゲタカファンドに日本人の預金運用権を売り飛ばしました。そのうえ、さらに国富を外資に明け渡す政策が「構造改革特区」や「国家戦略特区」。加計問題の本質は、特区という、アメリカの強要といってよい新自由主義政策にあります。特区というものを廃止しないかぎり、これからも不祥事が出そうです>
特区とは、政治介入を前提とした制度だ。そこで事業者と権力者の癒着が起きるのは必然的だ。
日本を危機から救うためには教育を立て直す必要がある。
藤原氏は、<小学校のあいだはひたすら本を読み、知識と教養の土台を築くしかない。中学・高校になれば科学や歴史も大切になる。したがって小・中・高では携帯・スマートフォンを禁止、少なくとも使用を大幅に制限すべきです>と主張する。
評者も同じ考えだ。スマートフォンを持っている児童や生徒は、ゲームやSNSで時間を浪費してしまう。本を読む時間も、1人でゆっくり考える余裕もなくなってしまう。国語の読解力を着実に身につけることができる教育体制への転換が必要だ。 ★★★(選者・佐藤優)
(2020年4月9日脱稿)