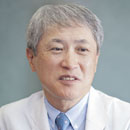「伸びる心血管修復パッチ」はどれくらい画期的なのか
そんな中、大阪医科薬科大、福井経編興業、帝人が開発した新たな心血管修復パッチ「シンフォリウム」は、体内で分解・吸収される糸(PLLA糸)と分解されない糸(PET糸)で編み込んだニット構造の生地をゼラチン膜でコーティングした製品で、患者さんの成長に合わせて伸びるように作られているため、再手術の必要を減らせると期待されています。
パッチを心臓の外壁や血管壁に埋植すると、術後3カ月ほどで患者さん本人の細胞がゼラチンと置き換わって自己組織が再生されるうえ、2年ほど経過するとPLLA糸が分解されてPET糸だけになり、素材全体が2倍以上に伸びる構造になっているのです。
■耐久面も理にかなっている
子供の患者さんの成長とともに伸びる人工医療材料というと、いまから25年ほど前に米国の大学に招聘されて“伸びる人工血管”を研究している日本人医師がいました。右心室から大動脈、左心室から肺動脈が出ている先天性心疾患の完全大血管転位症に対して実施されるラステリ手術という術式があります。人工血管を用いて右心室と肺動脈の通路=心外導管を作り、血液を肺に流す手術です。このラステリ手術は1~2歳の頃に行われる場合が多いため、患者さんの成長とともに人工血管の直径が足りなくなってきます。そのため、再手術で血管を太くしていくのですが、患者さんの負担は大きく、リスクがアップします。