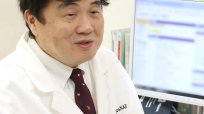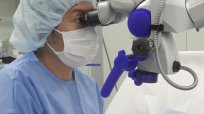若年性認知症は早期発見、早期予防…「未病」の間に見つけ出し、発症を食い止める
65歳未満で発症する若年性認知症は、平均して50~51歳くらいで発症する方が多い。私の外来でも50歳前後に診断されたという患者さんが大半です。
ですから、治療の目標は、60歳の定年まで仕事を続けることとしています。仕事をしている方が生活のリズムができやすいですし、適度に体を動かすので夜も眠りやすくなります。仕事があると、本人も患者さんも心のハリを保ちやすいという点もあります。
進行を遅らせるためには若年性認知症においても、早く見つけ早く介入することが重要です。かつては「早期発見、早期治療」とうたっていましたが、それよりも「早期予見、早期予防」が肝要。早期発見、早期治療は、発症したら(症状が目立つようになったら)できる限り早く発見し、治療に結びつけましょうということ。一方、早期予見、早期予防は、発症する前、つまり未病の間に発症の「芽」を見つけ出し、発症しないよう手を打つことになります。
若年性認知症の発症までの経緯を説明しましょう。なお、これは65歳以上の一般的な認知症も同様です。
発症より25年ほど前から脳にアミロイドβというタンパク質がたまり始め、やがてタウというタンパク質がたまり、それらが異常タンパクとして脳の中でさまざまな反応を起こし、神経細胞が壊れ数が減っていきます。
この過程で記憶に関するアセチルコリンという物質の数が減り、記憶障害をはじめとする認知機能低下の症状が現れ始めます。MRIやCTなどの脳の画像検査をすると脳の萎縮が見られ、特に若年性の場合は海馬ではなく頭頂葉に目立つという特徴があります。認知機能を評価する簡易テストMMSEなども実施し、現在の臨床症状、今までの経過、血液検査結果などを参考に、総合判断のもと認知症と診断されます。
認知症の進行段階は「正常→SCD(主観的認知機能低下)→MCI(軽度認知障害)→認知症の軽度→認知症の中等度→認知症の高度」となります。早期予見で狙うのはSCDやMCIです。
MCIの後半になると日常生活や仕事には支障がないものの、周囲がうすうす気づく認知機能低下が出てきますが、MRIやCTではわかりません。だから長らく早期予見につながらなかったのです。
しかし認知症の原因物質アミロイドβの蓄積を測定する検査機器アミロイドPETの登場で可能になりました。