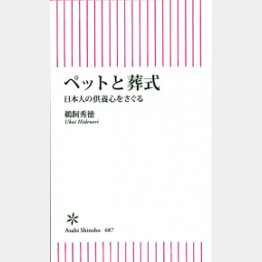「ペットと葬式 日本人の供養心をさぐる」 鵜飼秀徳著/朝日新書 2018年
著者の鵜飼秀徳氏は、宗教の内在的論理がわかる稀有なジャーナリストだ。「寺院消滅」「無葬社会」(いずれも日経BP社)など、現下日本の宗教が抱える問題を、丹念な取材と強靱な思考力によって、すぐれた作品を世に出している。
今回は、ペットの死をめぐる問題に、現状の取材と歴史的考察をあわせて総合的に扱っている。東京・両国の回向院(浄土宗)には、1816(文化13)年に建てられた「猫塚」がある。
<由緒書きには「猫の恩返し」と題名が記され、こう書かれていた。/「猫をたいへんかわいがっていた魚屋が、病気で商売ができなくなり、生活が困窮してしまいます。すると猫が、どこからともなく二両のお金をくわえてき、魚屋を助けます。/ある日、猫は姿を消し戻ってきません。ある商家で、二両くわえて逃げようとしたところを見つかり、奉公人に殴り殺されたのです。それを知った魚屋は、商家の主人に事情を話したところ、主人も猫の恩に感銘を受け、魚屋とともにその遺体を回向院に葬りました」>
猫好きの読者ならば、じんとくる話だ。評者も猫を5匹飼っている。そのうちの2匹は今、筆者の仕事机に寝そべって、キーボードを打つ筆者の姿を見ている。評者も猫からエネルギーを得ているような気分になる。
鵜飼氏は、<たとえば子どもの頃、かなりの割合の人が金魚を飼育した経験があるのではないか。屋台で金魚すくいをやって、持ち帰って金魚鉢などで飼育するのは夏の風物詩でもある。/しかし、大抵はワンシーズンで死なせてしまう。私も私の小学3年生になる息子も同様のことを経験している。小さいいのちを粗末に扱ってしまったとの反省も込め、その死後、遺体は無下に扱えない心情になる>と書いている。
金魚すくいでとった金魚、林や野原で捕まえたクワガタムシ、カブトムシ、ダンゴムシなどの飼育を通じて、子どもたちは死をリアルに感じるのである。小さな命を粗末に扱ってはいけないと思うところから、他者をたいせつにする心情が育ってくる。犬や猫など、人間との関係が緊密なペットを飼うことを通じて、人間の魂も成長していくのだと思う。
★★★(選者・佐藤優)
(2018年10月19日脱稿)