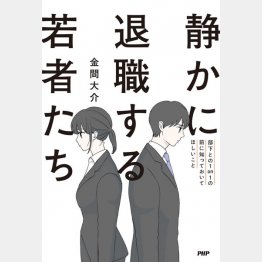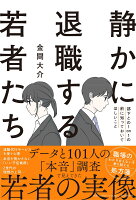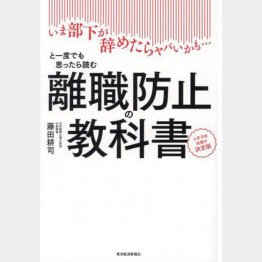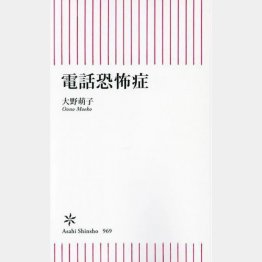ちかごろの静かな若者
「静かに退職する若者たち」金間大介著
反抗的ではないが反応も薄く、なにを考えているのかワカラナイ。ちかごろの若者論。
◇
「静かに退職する若者たち」金間大介著
「ちかごろの若いモンは」は古代ギリシャでも決まり文句だったそうだ。だが、現代はなにを考えているのかわからないまま、ある日突然「ボク、会社辞めます」と言ってくる若者たちが急増しているという。
そんな世の中の痛点にぐさりと刺さるのがこの書名。中間管理職なら書店で思わず手に取りたくなるだろう。企業や勤務先で通例の「ワン・オン・ワン」。1対1での面談は若い部下とのコミュニケーションに必須といわれるが、仲良くなることと勘違いする上司は少なくない。仲良くなるのではなく信頼関係の構築が大事なのだが、著者はズバリ「(上司の)年齢が上がれば上がるほど、この区別がつきにくくなっている」という。
著者は物理学で博士号を取得しながらアメリカ留学中に当時最先端の「イノベーション・マネジメント」論に魅了され、専門を変えたという金沢大教授。学生と接する経験もふまえ、ちかごろの若者は「いい子症候群」と指摘する。目立ちたくない、人前でほめられるのが「圧」。オススメの資格は自分の目標次第というと「お話ありがとうございました」と丁寧に挨拶し、「どんな目標にどんな資格が有効か教えてください」と来るのだそうだ。
ではどうすればいいか。その答えは本書で(笑)。 (PHP研究所 1870円)
「離職防止の教科書」藤田耕司著
「離職防止の教科書」藤田耕司著
人手不足はいぜんとして深刻。若手の離職を止められなかった上司が人事考課で降格されるなどが普通の現実だ。本書は、大手会計事務所勤務の経験がある公認会計士・税理士かつ経営心理士の資格も持つという著者が離職防止を指南する。
必要なのは「4つの欲求」に訴えること。第1は生存欲求。部下は上司の働き方を見てその職場での未来を判断する。第2は関係欲求。人間関係が原因の離職は本音を言わないので問題の所在がわかりづらい。第3は成長欲求。転職サイトのキャッチフレーズも「成長」だ。そして第4が「公欲」。働く喜びの根底にあるのはやりがい、つまり社会に役立っているという自覚だ。
第6章では年代と意欲・能力別の離職防止策を伝授するなど、きめ細かさが持ち味だ。 (東洋経済新報社 1980円)
「電話恐怖症」大野萌子著
「電話恐怖症」大野萌子著
職場で自分の目の前の電話が鳴るとギクッとする若手。自分から取引先にかけるのも苦手で、できるだけ周囲に聞かれたくないという。
本当の話? と疑う人は本書の著者に聞けばいい。産業カウンセラーとしてあちこちの企業に出かける著者は、ある出版社で筆者に電話する若手の社員が、廊下の片隅でしゃがみ込むような姿勢でひそひそと小声でスマホに向かう姿を目撃したという。著者によれば職場での雑談が減り、隣席の同僚とさえオンラインのチャットで会話する世の中になったのも一因とする。
もちろん現状の分析だけでなく、本書は終章で電話のかけ方も指南する。たとえば謝罪の電話では「すみません」では伝わりにくい。「申し訳ございませんでした」のほうがよいなど具体的なアドバイスが並ぶ。 (朝日新聞出版 924円)