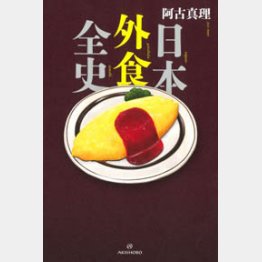「日本外食全史」阿古真理著
現今のコロナ禍においてもっとも深刻なダメージを受けているのは外食産業だ。2020年の1年間に倒産した飲食店は780件と過去最高。売り上げは前年比84・9%、中でもパブ・居酒屋は50・5%と半減。
本書は、くしくも「外食元年」とされる1970年から50年目の節目で起きたこの艱難(かんなん)を踏まえて、日本の外食の歴史を広範に見渡し、外食の意味を改めて問うている。
1970年の大阪万博では143の食堂、267の売店が置かれた。この万博はケンタッキーフライドチキンはじめインド本場のカレーなど、初めて世界の味に接する場所であり、同時にチェーン店方式で外食が産業化する時代の幕開けでもあった。
同年、すかいらーく、フォルクスの1号店が登場、翌71年にはマクドナルド、ロイヤルホスト、ミスタードーナツ、72年にモスバーガー、ロッテリアなど今も知られる人気チェーン店が相次いで産声を上げる。この外食ブームの後押しをしたのが、マンガの「包丁人味平」「美味しんぼ」、テレビの「大食い選手権」「料理の鉄人」などの各種メディアだ。本書ではこれらグルメブームをもり立てていくメディアの動向も検証している。
といっても、70年以前に日本に外食がなかったわけではない。江戸時代のおでん、そば、すしといったファストフードに始まり、明治期の肉食時代の到来とともに登場した牛鍋(すきやき)、焼き鳥などの肉料理、コロッケ、とんかつ、カレーライスといった「洋食」など、著者は前史ともいうべき時代の日本の食文化に対しても細かな目配りを欠かさない。
さらには、フランス料理、イタリア料理、中国料理、アジア料理などを個別に取り上げ、画期をなす人物や店を軸にそれぞれの料理の世界へ分け入っていく。
「全史」というタイトルにたがうことなく、600ページを超える本書は、文献やネット情報をふんだんに駆使して、いかにして日本に外食文化が定着していったかの歩みを詳細に後付け、外食産業の未来をも見据える。
今後も長く残る労作だ。 <狸>
(亜紀書房 3080円)