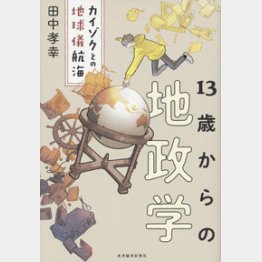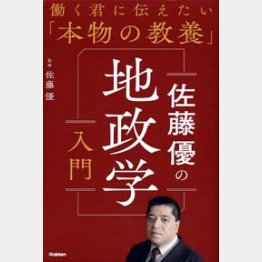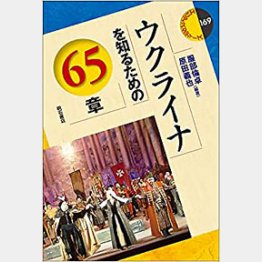国際関係を理解するカギ「地政学本特集」
「2030半導体の地政学」太田泰彦著
ロシアのウクライナ侵攻で黒海沿岸地方の複雑な地理と歴史と政治の絡み合いが注目された。「地政学の目」がこれからの国際関係を理解するカギなのだ。
◇ ◇ ◇
かつて世界一だった日本の半導体産業。しかし今、日本勢は見る影もなく、台湾と韓国にシェアを握られ、さらに米中が半導体戦争を繰り広げようとしている。日経新聞記者として半導体産業の盛衰を長年見てきた著者は、半導体を「工業製品であると同時に、政治的にユニークな特性がある」という。昔ながらの地政学は地理的条件と国際政治の関わりを考える方法論だが、現代の地政学は「陸と海を制するだけでは、優位に立つことはできない」という。半導体産業は一国の経済の柱になると同時に、現代のハイテク戦争の帰趨を左右する重要な要素になるからだ。
現にアメリカではバイデン大統領が就任して間もなく、アメリカの半導体サプライチェーンを強化するために補助金を捻出するシナリオ作りに着手。半導体のほかレアアース、医薬品、EV(電気自動車)部品用の電池のサプライチェーンを100日間で調査するよう関係省庁に指示する大統領令に署名した。米中新冷戦が指摘される現在、半導体が持つ地政学的な価値は計り知れない。2030年は、もう目の前なのだ。
(日本経済新聞出版 1980円)
「13歳からの地政学」田中孝幸著
主人公は高校1年生の大樹と、妹で中学1年生の杏。彼らは通学路にあるアンティークショップで、地球儀に目を奪われる。190センチもあろうかという大男の店主・カイゾクは、「7日間、わしの話を聞けばあげてもいい」と提案。かくしてレッスンが始まった。
地球儀を見ながら店主は「世界中の貿易は9割以上が海を通る。つまりアメリカが超大国といわれるのは、世界の船の行き来を仕切る国だから」という海と経済の話から、「戦争に勝ったカリスマでなければ選挙なしにリーダーであり続けるのは難しい」など大国の事情まで、世界の仕組みをレクチャー。やがて2人は「地球の中心はどこか」の問いについて考えていく……。
本書は世界40カ国以上で政治や経済、文化まで幅広く取材し、20年を超えるキャリアを持つ国際政治記者が、ジュニア小説の仕立てで地政学の基礎を教えてくれるユニークな本。
地政学は現代の理解に必須といわれても、なにやらムズカしそうな印象はぬぐえないが、国際体験豊富な店主が具体的な世界情勢を例に教える地政学はすっと頭に入ってくる。
(東洋経済新報社 1650円)
「佐藤優の地政学入門」佐藤優監修
かつて外務省の腕利き分析官として冷戦末期のソ連からロシアを担当した著者。地政学を語るには最適の人材として、本書では現代の若手世代に地政学を講義する。
実は地政学は戦前のドイツでナチスの御用学となった暗い過去がある。国家は国力に応じた資源を得るための「生存圏」を獲得するのを当然の権利だとし、さらに国家の発展のためには「経済的支配地域」の確立を必要とする。そんな論理でポーランドに侵攻し、ヨーロッパから世界全体を戦争に引きずり込んだのだ。
さらに戦後になるとイギリスのマッキンダーが現代地政学を発展させ、「ランドパワー」(大陸国家)と「シーパワー」(海洋国家)の対立が世界情勢の機軸となると説いた。米ソ冷戦しかり、現代の米中新冷戦も同じだろう。
著者は地政学を知ることで世界情勢や各国の思惑が見え、状況分析や未来の先読みが可能となり、さらにはビジネスにもこの視点を活用できると説く。地政学はいわば21世紀の日本を率いる世代に必要な“教養”なのだ。
(学研プラス 1480円)
「日本の経済安全保障」渡邉哲也監修
作家でビジネス評論家が監修した本書は、地政学ならぬ「地経学」のススメ。現代の安全保障のカギを握るのは、グローバリゼーションのもとでかつてとは大きく変容した経済関係だ。ウクライナ侵攻に対する西側諸国の制裁でロシアのルーブルは孤立し、ロシア産のガスの大口顧客ドイツでも取引停止を求める世論が盛り上がっている。
本書はこの地経学的な観点に立って、これからの経済安全保障をどうすべきか、そのために必須の心構えを伝授する。
たとえば日本は経済安保を「自国の基幹産業を守る」ための戦略として利用するが、中国の場合、アフリカ諸国への進出の例にあるように経済援助の代わりにその国の資源開発の利権を入手することに重きを置く。つまり経済安保を「自国がより強くなる」ための戦略として使うのだ。こういう積極性が、近年、中国で聞かれる「アメリカ型民主主義とは違う中国型のデモクラシー」などという論法の背景になっているのだろう。東アジアの地政学と地経学から見るなら、中国とのデカップリングを急ぐべしとの主張も説得力があるだろう。ロシアとのビジネス停止が遅れて評判を落としたユニクロの失敗例に学ぶべきときだ。
(宝島社 1540円)
「物語 ウクライナの歴史」黒川祐次著
今回のロシアによる侵攻でウクライナがここまで持ちこたえて抵抗するとは予想できなかった、という声があるが、それは歴史を知らない人だろう。古くはスウェーデン、リトアニア、ポーランド、かつてのロシア帝国、オーストリア=ハンガリー帝国、そしてソ連邦と、東から西から北から度重なる圧力と侵略を受けながらも、ウクライナは忍従して独自性を失わず、各地に有為の人材を送り出してきた。その人口およそ5000万人。今回の侵攻でバルト海地方や欧州全体に占めるウクライナの地図を何度となく見たが、実は欧州では第2の国土面積を持つ。駐ウクライナ日本大使をつとめた元外交官の著者が「ヨーロッパ最後の大国」と呼ぶゆえんである。
ただし大国ゆえに地方によって風土や気質が異なり、国全体としてのアイデンティティーは実は意外に強くない。ゼレンスキー大統領も、親ロシアと反ロシア双方の勢力の隙間から躍り出たシロウト政治家だったことを忘れるべきではないだろう。宗教もロシア正教が強い東部と東方典礼カトリックが主流の西部とかなり異なっている。地政学にはこういう視点も必要だ。そんな深い話に入る前の入門書として手頃だろう。
(中央公論新社 946円)
「ウクライナを知るための65章」服部倫卓、原田義也編著
今回の侵攻でゼレンスキー大統領はNATO(北大西洋条約機構)の支援と自国の加盟を切望したが、地図を見ると意外に微妙な話なのがわかる。ウクライナが国境を接するのはロシア、ベラルーシ、ポーランド、スロバキア、ハンガリー、ルーマニア、モルドバ。黒海をはさんで向かいはトルコだ。それらの地理は絶対的な条件である上に、折々の情勢につれて揺れ動く政治的側面、経済的利害、人の移動、宗教や言語などがからんでくる。
本書はそんなウクライナを知るための知的ガイドブック。歴史だけでなく、国民のアイデンティティーや言語、宗教、またウクライナでも目立つオリガルヒ(新興財閥)やチョルノービリ(チェルノブイリ)原発事故のその後など、現在の関心事に直接結びつく事項が多数並んでいる。
もとは2014年のロシアによるクリミア併合をきっかけに編集されたようだが、その後のドンバス内戦などをふまえて増補され、今回も店頭でよく目にする。いまでは「キーウ」と表記変更された「キエフ」の呼称についても断り書きがあるなど、専門家が集まっただけに配慮も早くからあったのがわかる編集内容だ。
(明石書店 2200円)
「世界滅亡国家史」ギデオン・デフォー著 杉田真訳
地政学は地理と政治状況のほかに、その地域における歴史的ないきさつが重要な視点になる。「世界一ニッチな世界史」とオビに銘打った本書は、近現代史の上で国際的な認知が得られず、文字どおり「泡(バブル)のように」消えた48の国を列伝形式で紹介した歴史エッセー。著者はイギリスの作家でアニメ脚本家だが、もとはオックスフォード大学で考古学と人類学を学んだというインテリだ。
たとえばいまはマレーシアに属するボルネオ島北部に生まれた「サラワク王国」は、イギリス人ジェームズ・ブルックがブルネイの王族から「英国王の代理人」と勘違いされて領土をプレゼントされてできた国。ブルックは英雄ともてはやされたが、その後、世評は地に落ちた。まさにイギリス帝国主義の歴史の縮図のようだ。
また厳冬のフィンランド湾に浮かぶナイッサールは、ロシア革命の最中、労働無政府主義者の艦長に率いられたロシアの戦艦ペトロパブロフスクが80人の乗組員で占拠し、「ナイッサール兵士・要塞建設労働者ソビエト共和国」を樹立した地。しかしこのソ連邦最初の国はボリシェビキ政権への反乱を企ててすぐに鎮圧され、姿を消したのだ。
(サンマーク出版 1650円)