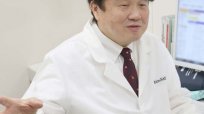思春期の子供の不登校の原因は「起立性調節障害」かもしれない
「異常を見つけ、正常にするための正しい方法だけを伝えても意味がありません。『夜中までゲームをしていた』という言葉に『だから朝起きられない』と返せばそこで終わってしまいますが、『そうやって過ごすのが楽だったんだね』と応じれば、次の言葉が出てくるかもしれません。子どもが何を話しても大丈夫と思える信頼関係を構築し、全体像を見渡した上で子どもの現在地を把握する視点が求められます」
子どもが「学校に行きたい」「起きられるようになりたい」と言っても、今すぐ実現したい欲求とは限らない。「親を悲しませたくない」「普通でありたい」「そうしなくてはならない」といったところから来ているかもしれない。子ども自身が渇望しているものを見つけ、そこに向かう状況整理をするのが専門家や親の役割となる。
「できないことではなくできることから広げていく。朝は起きられないけど夕方に友達と遊べそうというなら、治療として推奨し、できた場合には褒めます。『不登校なのに夕方に友達と遊ぶなんて』という気持ちがあるなら、そう思わない環境整備をしていきます」
よくある親の誤認は「朝起きられない=学校に行けない=治っていない」。これは回復の過程を狭めてしまう。「朝は起きられないが夜は元気」というところに意味を見いだし、これからどう整えていくかを共に探っていくことが重要だ。