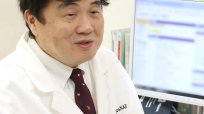“病は気から”の仕組み解明 引き金は脳内の微小炎症だった
「病は気から」と昔から言われるが、慢性的なストレスが消化器の機能障害や突然死をもたらす仕組みを、北海道大などの研究チームがマウスの実験で初めて明らかにした。ストレス性の病気や突然死の予測に役立つという。論文は4日までに、国際科学誌イーライフに掲載された。
北大遺伝子病制御研究所の村上正晃教授らは、マウスに睡眠障害を起こして慢性的なストレスを与える実験を実施。自分の組織を攻撃してしまう免疫細胞(病原T細胞)を静脈に注射すると、胃や十二指腸の炎症、出血が引き金となり、心臓機能が低下して突然死した。
ストレスのみを与えた場合や、ストレスを与えず病原T細胞を注射しただけの場合、死ぬマウスはいなかった。
突然死したマウスを詳しく調べると、病原T細胞が脳の特定部位に集積して微小な炎症を起こしていた。
この部位に炎症が起きると、新たな神経回路が形成されてよりストレスを強め、消化器などの炎症を引き起こすことも判明した。
逆にストレスがなく、ストレスに反応する交感神経が活発に働いていない状態では、脳内への病原T細胞の集積や微小炎症が起きないことも分かった。
病原T細胞の有無は人によって異なる。研究チームは血液検査で病原T細胞を調べることにより、ストレスによる疾患や突然死のリスクを予測できる可能性があるとしている。