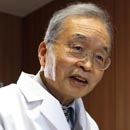口腔がんの手術に臨んだ外科医の「気構え」が忘れられない
その後、がんは小さくなり、痛みも楽になったと聞いて、私もホッとしました。さらに「今後は某大学の口腔外科の医師とG病院の外科医とで連携しながらAさんを診ていただきたい」とアドバイスしました。
■緩和医療が進んだのはとても良いことだが…
この出来事で、私は自分の学生時代を思い出しました。もう50年以上も前のことです。当時は「緩和」という言葉はありませんでした。
私は原因不明の耳鳴があって、よく耳鼻科の医局に出入りしていました。夏休みのある日の朝、医局でお茶を飲んでいたら、教授から「佐々木君、これから手術に入る。見るか?」と声をかけられました。私は教授が自分の名前を覚えてくれていたことがうれしくなり、「はい!」と答えました。
手術室に行き、手洗いをして、手術着に着替えました。患者は右の頬が大きく腫れた70代の男性で、手術は「上顎洞がん摘出術」でした。上唇の中央部から鼻翼の右側、右目の下まで縦に切開し、皮膚をはがし、大きな腫瘤を摘出するのです。右上顎から鼻腔、頬骨も切って上顎洞、ほとんど顔の右側半分を切除しました。