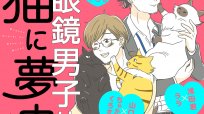日比谷高校の東大合格者数“復活”に尽力した3人の立役者
「一中、一高、帝大」とは、戦前のエリートコースの代名詞。帝大(東京帝国大)は現在の東大、一高(第一高等学校)は東大教養学部前期課程、そして一中(東京府立第一中学)が都立日比谷高校(東京・永田町)である。
一中はいわば、日本のエスタブリッシュメントへの入口だったわけだが、それは戦後に日比谷高となっても変わらなかった。1965年までずっと東大合格者数トップ。64年には192人もの合格者を東大に送り込んだ。この記録は2012年に開成高が203人という驚異の数字を叩き出すまで半世紀近く抜かれることはなかった。
66年、都立西高にトップの座を明け渡したが、翌年再び返り咲き、日比谷高の天下は当分、続くかと思われた。だが、まもなく凋落が始まる。その原因は「日比谷つぶし」とも言われた67年からの都立高の学校群制度導入である。学区内に2~4校の群をつくり、合格者をそのグループ各校で振り分けるという方式だ。都立高の格差をなくし、加熱する受験戦争を緩和するのが狙いだった。日比谷高は九段高と三田高と同じ群になった。
「日比谷を目指してせっかく合格したのに、九段や三田に振り分けられ、それを蹴って私立に行った同級生が少なくなかった」と振り返るのは、学校群制度導入3期目に日比谷高に入学したOB。