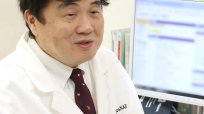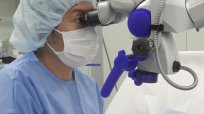若年性認知症(3)65歳以上の発症と比べて症状の進行が速い傾向
新薬は効果の持続時間は10カ月だが、早く使うほどメリットがある
新薬と従来薬の大きな違いは、新薬が認知機能の低下を継続して遅らせる根本的治療薬であるのに対し、従来薬は神経伝達物質を補充する対症療法であるため期間限定的な点です。
認知症の7割を占めるアルツハイマー病は、アミロイドβという原因物質の蓄積から始まり、25年ほどかけて脳の神経細胞のダメージへと至ります。
アルツハイマー病発症までの流れは川の流れに例えられます。
いわば川の上流が、アミロイドβの蓄積の始まり。水が流れ着いた先である下流が、脳の神経細胞のダメージ。新薬は上流に、従来薬は下流に働きかける薬で、それゆえに従来薬は新薬と比べると効果の持続期間が限定的です。
だいたい10カ月ほどで効きづらくなるとされています。
「1年もしないうちに効果を得られなくなるのでは、使う意味がないのでは」という意見も、一般の人ではあるかもしれません。しかし、10カ月という期間でも、薬を使うことで無気力の状態が改善したり活気が出たりすることがあります。症状が軽いうちに使い始め、「脳のモヤモヤが取れた」「脳がハッキリした」という感想を漏らす患者さんもいます。しかも、その10カ月というのは平均であって、それよりも長く有効性が見られる方もいるわけです。
定年まで働くことを目指す若年性認知症の患者さんにとっては、症状の緩和が、仕事のやりやすさ、周囲とのあつれきの減少につながるでしょう(認知症ではイライラするなどの症状もあり、周囲とのトラブルの原因になることもあります)。
なお、「若年性認知症と仕事」という観点から言いたいのは、これまでヒットした映画やドラマの中には、若年性認知症の描き方が正しくないものがあります。発症したら数年で仕事ができなくなる──。そんな印象を抱かせる内容になっています。
進行スピードは個人差があるものの、MCIから認知症に進行するまで約5年、認知症軽度から中等度まで5~8年。この目安は新薬が登場する前から言われているものなので、新薬の効果で進行がもう少しゆっくりになるかもしれません。
若年性認知症の進行に伴い仕事の内容を変える必要はあると思いますが、中等度くらいまで仕事を継続できるとすると、「数年で仕事ができなくなる」ということはないのです。
本連載の担当者が20年ほど前に取材した若年性認知症の方は、製薬会社のMR(医薬情報担当者)ということもあり病気の知識があった。それもあって、早い段階で専門機関を受診し、診断に結びついたそうです。
会社の上司と交渉し、認知症の症状が出ても仕事を継続できる部署へ異動し、定年間近まで勤務。自分が働けなくなった時のことを考え、利用できる国の制度に申し込み、さらには家族との思い出を作るために、自ら計画を立て、旅行にも何度か出かけたそうです(これらのお話は、奥さまから聞いたものです)。
認知症になっても人生は、家族も含めて終わりじゃないということを示すエピソードだと思います。