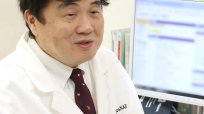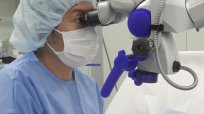若年性認知症は早期発見、早期予防…「未病」の間に見つけ出し、発症を食い止める
MRIやCTでは認知症を早くに見つけることは難しい
読者の中には脳ドックを受けたことがある方もいるでしょう。脳ドックでは一般的に、脳の画像検査MRIやCTを行います。MRIやCTは脳の形を見る検査で、脳梗塞や脳動脈瘤の発見は得意です。しかし、脳の萎縮が明らかになるまで、つまり認知症を発症するまでは異常を検出できません。早期予見で見つけ出したいSCDやMCIは、MRIやCTではわからないのです。
一方、アミロイドβの脳への蓄積を調べるアミロイドPETは、認知機能の低下が現れていない段階(SCD、MCI)でも、今後の認知症発症のリスクを調べることができます。アミロイドβの量を調べる検査として脳脊髄液検査もありますが、脳脊髄中のアミロイドβの量から脳のアミロイドβ量を推測する検査になりますので、脳のアミロイドβを直接調べられる検査はアミロイドPETだけになります。
なお、がんを調べるときに使うPETと、アミロイドβを調べるアミロイドPETは、使う検査機器は同じで、薬剤が異なります。
私が診た患者さんでこんなケースがありました。若年性認知症で、認知機能評価の簡易テストMMSEの結果からMCIと診断された2人の患者さん。MRIや脳SPECT(脳の血流や機能を画像化する検査)の結果も同様でした。しかしアミロイドPETをすると、ひとりはアミロイドβが蓄積しており、もうひとりは蓄積していませんでした。また、別の患者さんになりますが、MRIでは明らかな海馬の萎縮が見られたのに、アミロイドPETをするとアミロイドβが少ないという結果でした。
認知症には、アミロイドβの蓄積が多いアルツハイマー型もあれば、アミロイドβ量とは関係していない認知症(アルツハイマー型以外の認知症)もあるのです。
2023、24年に承認された新薬は、いずれもアミロイドβに働きかけるものです。この新薬の対象となる条件のひとつが、アミロイドβの蓄積が確認でき、ある一定量を超えていること。
若年性認知症でアミロイドβの蓄積が確認できた患者さんは、新薬を用いながら、認知症発症に至らない、もしくは至るのを遅らせる治療を受けられることになりました。ただし、アミロイドβの蓄積が確認できなくても、生活習慣病の治療、脳を活性化させる運動、生活習慣の改善など、打つ手は複数あり、認知機能の低下を遅らせられます。